夏から秋にかけて水深のあるサーフでは、ベイトを追って青物が回遊してきます。
シーズン序盤は30㎝未満の小物が多いのですが、後半になると60㎝超えるサイズも混じります。
ヒラメやマゴチを狙っていて、不意に大型の青物を掛けて悔しい思いをした方も多いはずです。
そこでこの記事では、サーフから青物を狙うときに最適なPEラインの太さ(号数)について解説します。
細くて強いおすすめのPEラインもご紹介するので、参考にしてください。
PEラインの太さがサーフショアジギングに与える影響

サーフから青物を狙う釣りはサーフショアジギングと呼ばれており、主にメタルジグを使います。
重量のあるルアーをフルキャストして、引きの強い青物を狙うのでラインブレイクという観点だけを考えると太い方が有利です。
ただし、PEラインを太くすると新たなデメリットが生まれることを理解しておく必要があるでしょう。
オフショアで使用するような太いPEラインを使えばよいという訳ではありません。
飛距離
サーフショアジギングで青物を狙うときに、最も大事なことは飛距離を武器にすることです。
ヒラメやマゴチのように波打ち際でのHITは少なく、ほとんどが遠投先でのHITです。
ラインは細いほど空気抵抗が減るので、飛距離は伸びますが細いと弱くなります。
そのため、青物の強い引きに耐えられるギリギリの太さを選ぶことが大事です。
風・波
無風で波が静かなサーフでは、PEラインを太くして飛距離以外に大きな影響はありません。
しかし、横風が強い状況では風にあおられてラインスラックが釣りの邪魔をします。
また、波にまかれてルアーの動きが破断しやすくなるので、青物に見切られます。
基本的にサーフショアジギングは釣れない時間が長いので、ストレスなく釣り続けることは非常に大事です。
スプールに巻く糸の量
ラインを太くするとスプールに巻ける量が減るので、使用するリールの番手によってはラインのキャパ不足に陥ります。
PE1号を200m巻けるリールに2号を巻くと100mしか巻けないことになります。
青物はHITした瞬間、沖に向かって全力で走るため、場合によってラインを出されて切られるでしょう。
そのため、サーフショアジギングで大型の青物を狙う場合は5000番リールを使うこともあります。
サーフショアジギングで青物を狙う最適なラインの太さ(号数)

サーフショアジギングで狙える魚の代表格は、青物と呼ばれるブリやカンパチの若魚です。
場所によってはシイラやソーダガツオ、サワラ(サゴシ)も狙えますし、当然ヒラメやマゴチもターゲットに含まれます。
サーフはアタリが少ないので、青物以外の魚も考慮してラインの太さを選択する方が楽しい釣りを実践できます。
| 太さ | 魚種 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| PE2.0号 | ・大型の青物(60㎝以上) ・オオニベ | ・重いルアーをキャストしても高切れしにくい ・大型の青物と真っ向勝負できる | ・風や波・潮の影響を受けやすい |
| PE1.5号 | ・大型の青物(60㎝以上) ・オオニベ ・ヒラメ ・マゴチ ・シイラ | ・様々な大物に対応できる太さ ・無茶してもラインが切れる心配はない | ・風や波・潮の影響を受けやすい ・無理するとフックやスプリットリングが変形してバラす |
| PE1.2号 | ・中型の青物(40~60㎝) ・オオニベ ・ヒラメ ・マゴチ ・シイラ | ・ギリギリ大物と対峙できる ・ラインスラックを出しながらアプローチしやすい | ・30g以下のルアーは使いにくい |
| PE1.0号 | ・小型の青物(40㎝以下) ・ヒラメ ・マゴチ ・シイラ ・ソーダガツオ | ・風の影響を受けにくい | ・ルアー操作が案外難しい ・大型の青物とは対峙できない |
PE2.0号を使うメリット・デメリット
PE2.0号を巻いておくと、重量のあるメタルジグをフルキャストしても高切れが起きにくくなります。
また、大型の青物を掛けても無茶なファイトをしない限り、切られることはありません。
サーフは根ズレで切られる心配はないので、釣り経験が浅い方でも走らせて体力を奪えば獲れます。
ただし、波の影響を受けやすく、潮の流れでどんどんラインスラックがでるのでルアーのコントロールが難しくなります。
ドン深サーフでも完全に波に巻かれてラインテンションが戻る前にまた波にのまれて、ルアーの動きが全く分からないこともあります。
青物のハイシーズンである夏から秋は台風の風や波が残っていることもあるので、使いこなすテクニックも必要です。
PE1.5号を使うメリット・デメリット
PE1.5号を巻いておけば、青物だけでなくメータークラスのヒラメやオオニベも相手にできます。
掛けた魚は確実に獲り込みたいので、サーフジギング以外でも1.5号を使っています。
ただし、風や波、潮の影響は無視できず、慣れるまではグーっと引っ張られる違和感を覚えます。
また、ラインの強さを生かして無理し過ぎるとフックが伸びたり、スプリットリングが変形することもあります。
ヒラメやマゴチのレギュラーサイズに対してはオーバースペックですが、大物を獲りたい方はデメリットを考慮しても使うべきです。
PE1.2号を使うメリット・デメリット
荒れた日のサーフでPE1.5号を使うと、風と波の影響で釣りにならないときがあります。
そのため、大物を掛けてもギリギリ対応できる太さの1.2号を使用します。
PE1.0号に比べて耐摩擦、耐衝撃が体感できるほど向上するとは言い切れませんが、安心感を与えてくれるでしょう。
風や潮の流れを上手く使ってラインスラックを出しながらアプローチすることもできます。
デメリットは風や潮の流れを無視できないので、30g以下のルアーを使いにくい点です。
スーパーライトショアジギング感覚でサーフを攻略したい方は、ラインコントロールの技術を身につけてください。
PE1.0号を使うメリット・デメリット
PE1.0号まで細くすると、空気抵抗が減りルアーがラインを引っ張っていくので風の影響を受けにくくなります。
初夏の青物はサイズが小さく、シイラやソーダガツオも狙いやすい太さですので、PE1.0号でも問題ありません。
糸を張って巻きやすく、アクションがダイレクトに伝わるので釣れそうな気がします。
しかし、この状態はルアーの動きが無機的で魚に違和感を与えるので、実際は釣れません。
そのため、風や波を使ってラインスラックを出しながらアプローチするテクニックが求められます。
大型の青物を狙う方はPE1.5~2.0号、中型までならPE1.0~1.2号を選択!
サーフから青物を狙うおすすめPEライン3選
サーフから青物を狙う場合はファイト時間が長くなるので、「AVE.表記」を参考にドラグを調整しています。
走らせて時間をかけても平均強度を把握しておけば安心してやり取りできるでしょう。
よりシビアなラインシステムで大物と勝負したい方には、「AVE.表記」と「MAX.表記」を併記している「シーガー PEX8」をおすすめします。
【シーガー】PEX8(1.2号)
シビアなラインシステムで青物を狙う方におすすめ
このラインは「AVE.表記」と「MAX.表記」を併記しているので、シビアなラインシステムで青物を狙えます。
ギリギリまで細くても、的確なドラグ設定を行えるのでファイト中のラインブレイクが軽減されます。
コスパを追求したラインですが、性能が高いので信頼して使用できるでしょう。
しなやかなラインですのでメタルジグを繊細に動かせるため、食い渋る青物を狙うときにもおすすめです。
【東レ】スーパーストロングPEX8(1.5号)
ゴワツキが少なく使いやすいPEライン
昔からあるロングセラー商品であり、他社のPEラインに比べて使用感はゴワツキが少なくナチュラルです。
コーティングバリバリのラインは使用感がどんどん変化するので苦手という方にもおすすめします。
キャストフィーリングも同価格帯のラインの中ではワンランク上で、糸鳴りも気にならないレベルです。
結束強度も出しやすく、しっかり締め込めるのでFGノットを覚えている最中の方にもおすすめします。
【ダイワ】UVF PEデュラセンサー×8+Si²(2.0号)
ラインの細さにこだわるならコレ!
風が強く波が高い状況でPE2.0号を使い、大型の青物を狙うときにはラインスラックに悩まされます。
そのため、同じ号数でも細いこのラインを使って、釣りにくさを軽減しています。
細さを数値化して表記していませんが、同じ2.0号を巻くと他社製品より多く巻けるので細いと判断して間違いないでしょう。
耐久性、強度も問題なく、コーティングもしっかりしているので、シマノの蜜巻きリールとの相性も抜群です。
青物を狙うときに注意すべきPEラインの特徴

この記事では青物を狙うときに適したPEラインの太さについて解説してきました。
実はPEラインは曖昧な点が多く、太さ、強度に関して知っておくべきことが2つあります。
貴重な青物を掛けてラインブレイクを起こし、残念な思い出が増えないように知識として頭に入れておくとよいでしょう。
PEラインの太さはバラバラ
ナイロンライン、フロロラインに関しては号数が同じなら太さも一緒です。
これは日本釣用品工業会が2010年に定めた標準規格に基づいて作られているためです。
ラインの直径に対して基準を設けており、2号は0.235mmと定められています。
ただし、日本釣用品工業会に加盟していない正体不明の海外製はこの基準を満たしていないこともあります。
しかし、PEラインは原糸を編み込んで作られているので、直径が潰れており正確に計測できません。
そのため、代わりに9,000mあたりの重量を使ったデニール値で太さの表記を行っています。
このルールに問題はないのですが、デニール値の基準が曖昧です。
「PE糸の許容範囲は、上限・下限のデニールが、前後の号柄の標準値を追い越さないものとする」と決められています。
判りやすくいえば、0.8号と1.2号の間の重さ(デニール)に収めたら、1.0号になるということです。
同じ太さのラインを購入してリールに巻くと、余ったり足りなかったりするのはこのためです。
PEラインの強度表記はバラバラ
Eラインの強度はポンド(lb)で表記されており、ドラグ設定を行う大事な数字です。
この数字はメーカーが繰り返しテストを行って算出した数字なので信頼性には問題ありません。
ただし、メーカーによって表示している数字の内容が異なり、「AVE.表記」「MAX.表記」が混在しています。
当然、ドラグを設定するときに欲しい数字は平均的な強度を表す「AVE.表記」です。
ただし、数字のインパクトで強くみせるため多くのメーカーは「MAX.表記」をしています。
「MAX.表記」は最も高かった引っ張り強度を表しているので、この数字以下でも切れます。
そのため、3割ダウンでドラグを設定しなければ、思わぬタイミングでブチっと切れるでしょう。
釣り人として本当に欲しい数字は「min.表記」ですが、残念ながらこの数字を表記しているメーカーはありません。
また、ポンド数はどの試験結果なのか併記する決まりはないので、何も記載していなくてもOKです。
例えば「よつあみエックスブレイド アップグレードX8」は強くて使いやすいラインですが20lbのように数字だけ記載しています。
まとめ
サーフショアジギングを楽しむ方は、PE1.5号を巻いておけば小~大型の青物まで対応できます。
釣りやすさを重視する場合は、1.0号まで細くしても問題ありませんが、中型以上の青物を掛けると苦戦します。
私は1.5号を使用していますが、太いと感じる方は中間の1.2号を使うのもよいでしょう。







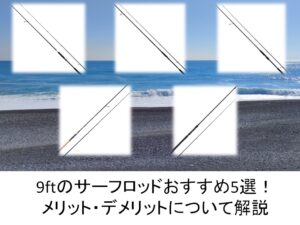




コメント